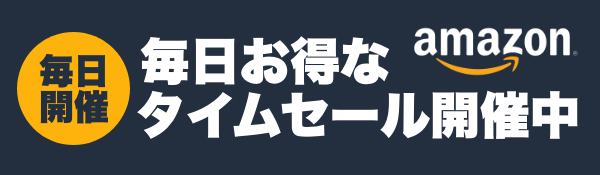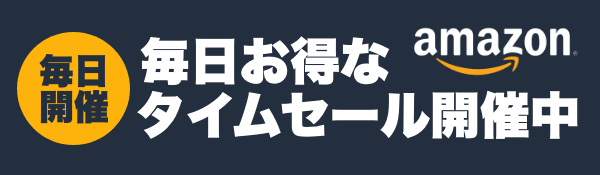土鍋のおすすめ10選!日本製の人気メーカーや選び方も紹介
土鍋というとおでんや鍋料理をするときくらいにしか使わないというイメージが強く感じますが、煮物のようなじっくりと時間をかけて調理をするようなレシピや、ご飯炊きにも使うことができて、持っているととても便利です。土鍋なんてどれを選んでも同じと思われそうですが、土鍋と言っても様々な種類のものがあり、いざ買おうとすると迷ってしまいがちです。そこで今回はおすすめの土鍋を紹介していきますので、参考にしてみてくださいね。
2019年07月04日更新
土鍋の特徴は?
鍋料理やおでんで必須とも言える土鍋は、その名前の通り土(陶器)から作られたお鍋なので、鉄製のものとは扱い方が少し変わってきます。陶器は急に高温にかけたりすると破損する危険性があるので、火にかける際には水などはしっかりと拭いて、弱火からじっくりと温めていく必要があります。信楽焼や万古焼といった陶器の土鍋が多い反面、最近はセラミック製の土鍋というものも登場しており、IHに対応していたりと、近代的な暮らしにもすんなり馴染むような特徴を持っているものもあります。
土鍋の選び方
素材で選ぶ
前述したとおり、土鍋は様々な素材のものがあります。そして、表面がなめらかであったり、荒かったりと、手触りも違います。蓄熱性の高さも、素材で変わってきますので、土鍋の特徴をしっかりと確認をしておくことも大切です。お手入れを簡単に済ませたいなら、セラミック製を選ぶと、汚れを落としやすいのでおすすめです。対応する熱源も素材によって対応しているものとしていないものがあるので、事前に自分が使いたい熱源に対応しているかチェックをしましょう。
調理するもので選ぶ
一括りに土鍋と言っても、様々な形のものがあります。おでんや鍋料理をするなら、比較的よく見かける浅めの形状のもので良いでしょうし、ご飯を炊きたいとなると、ご飯炊き専用の丸い形の土鍋も視野に入れてみると良いでしょう。基本的にご飯専用でなくても、深めな形状の土鍋なら、炊飯にピッタリと覚えておくと良いでしょう。鍋料理意外に蒸したりする用途で使用したい場合は、やはり熱伝導率が良い、浅めの土鍋を選んでみましょう。
大きさで選ぶ
土鍋を購入する際に、使用する人数などによって、選ぶ土鍋の大きさも変わってきます。一人暮らしの方が使用する程度なら、6号サイズで丁度良いでしょう。2~3人なら7号程度、更に人数が増えるなら、その上の8号、10号…と、サイズを大きくしていけば、理想の土鍋に出会えることでしょう。また、煮込み料理をする場合ならば、少し大きめのものを購入し、多めに作れば美味しく作ることもできるので、そのような選び方もおすすめです。
日本製土鍋のおすすめメーカーは?
長谷園
伊賀焼を代表するブランドの「長谷園」。天保3年(1832年)の発祥以来、伝統と技術を守り続け、「登り窯」や「大正館」などが国の登録有形文化財になっています。長谷園の中でも最も人気が高い土鍋が「かまどさん」です。最近では、お米を炊くのは炊飯器が主流ですが、そんな中でも75万台売り上げた大人気の土鍋です。特徴は、火加減調整が不要であること。かまどさんは従来の土鍋よりも1.5倍近い厚みがあり、ずっしりとした重みがあるため保温性にも優れ、短い加熱時間でお米の芯まで熱が届き、初心でもふっくらつやつやのお米を炊くことができます。またふたが上ふたと中ふたの二重になっており、この二重のふたが圧力釜の機能を果たすので吹きこぼれが全くしないのも特徴です。
三鈴陶器
萬古焼の有名ブランドといえば四日市の「三鈴陶器」。昭和40年の創業以来、ご飯鍋・蒸し鍋・燻製鍋・パエリア鍋など、幅広い料理に使えるオリジナル製品を多数作り続けています。三鈴陶器の耐熱陶器に対するこだわりは高く、厳選した6種類の耐熱陶土と、20種類以上の釉薬を組み合わせることでさまざまな質感の焼き物を表現。土の管理から焼き上げ過程に至るまで、熟練した職人の技術によって高品質なもの作りが保たれています。
ハリオ(HARIO)
「ハリオ」は1921年に創業した耐熱ガラスメーカー。コーヒードリッパーやサーバーが有名ですが、近年耐熱ガラス加工の技術を活かして開発した「ガラス製のフタのある土鍋」が注目を集めています。ドーム型のフタは、耐熱ガラス製になっており、内側の凸形状により、食材から出た水分が細かい水滴になり、循環させ、旨味を逃さない構造です。また直火・オーブン・電子レンジOKで500度以上に耐える耐熱陶器の土鍋は様々な熱源に対応しています。
![monocow [モノカウ] | 住まい・暮らしを豊かにするモノマガジン](https://monocow.jp/wp/wp-content/themes/monocow_ver2.0/images/logoimg.png)